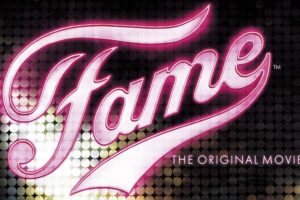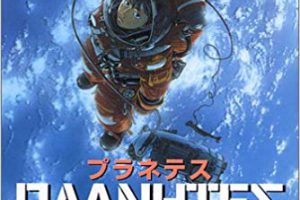NYを拠点として活動する20代前半の男の子たち。
まずは曲を聞いてほしい。
とりあえずメンバーバランスが素晴らしい。
黒人2人、白人2人、日系アメリカ人1人という人種構成は、まるで大人が時代背景を分析し、細部にまで配慮して作り上げたかのような最適解を思わせる。
しかし、このバランスは計算の結果ではない。
彼らはNYで最も有名な芸術高校の一つ、ラガーディア高校の同級生であり、親友同士で集まった結果、自然にこの多様性が生まれた。流石はニューヨーク。
楽曲以外のクリエイティブのレベルの高さも芸術系のエリート集団が作ってるんだと思うと納得。
MV以外にもメンバーの紹介動画があるんだけど、まるで映画レベルで「パッケージ」としての本気度を感じた。
いい曲だけじゃダメ。応援したいだけのストーリーテラーが必要って理解してるのすごいよ。
メンバー
- Jackson August(ジャクソン)
- Cisco Swank(シスコ)
- $eb (Sebastiano)(セブ)
- Yoshi T(ヨシT)
- Elijah Judah(イライジャ)
上から4人がMCで、最後のElijahが楽曲のまとめ役。
4MCなところとか5人で仲良くしてる画はリップスライムを感じるところもある。
ゴリゴリのヒップホップじゃないところとかも。
jenny’sという曲は今発表されてる中で最もポップな曲で「こういうのもやるんだ」と間口の広さを感じた。
このポップスとヒップホップのバランスを担っているのはJackson Augustで、彼はソロでインディー系の曲を作っている。
自分が作る音楽とは異なるヒップホップ寄りのトラックに自分の声が乗ったり、$ebがインディー寄りの「jenny’s」でラップしたりと、互いの世界観を交換し合って音楽を作るのが楽しいと言っていて、メンバー同士で相互に影響し合って実験してるのが微笑ましい。
Ciscoはジャズ・ピアノをずっとやっていて、徐々にラップに傾倒していったと話していたので、今後彼らの楽曲にジャズ的な深みが加わることを期待させる。
イタリア系の$ebは所謂ヒップホップ的な威圧感と自信のあるバースで、Jacksonと両極なバランス担当って感じ。
日系アメリカ人のYoshiは4人の中で最もラップが上手く、あんまり詳しくないけどMac Millerからの影響を強く感じた。
まだまだメンバーのことはよく知らないけど、少し調べただけでも色んな意味で色の違うメンバーが集まってる感じがわかったと思う。
Coachella出演
まだデビューして間もないがすでにCoachellaフェスティバルへの出演が決定している。
これに関しては批判的なコメントもちらほらある。
なぜなら彼らはライブの実績がほとんどなく、にも関わらず3大フェスの一つに出演できるということは、大手エージェントによって確保されているだろうと言えるから。
映画みたいなメンバー紹介やインディーとヒップホップを混ぜた楽曲、その他すべてのクリエイティブを名門美術系の学校出身の彼らだからこそこのクォリティだと思っていたが、DIY的な魅力が薄れてしまう可能性もある。
ここは大人の力なしに音楽業界で行きていくのはほぼ無理と念頭に置いたうえで、彼らのクリエイティブの邪魔をしない大人がついたと願いたい。
悪ノリに乗らないの偉い
品性を感じたのがインタビューでホストがDiddyのスキャンダルを揶揄する不適切なジョークを放った際、メンバーが冷静な態度でゴシップを流したところ。
場に合わせてすこし笑ったあとすぐに会話を音楽と才能の話題に引き戻したことは、彼らの品性と育ちの良さなどを感じた瞬間だった。
こういうところも好感持てる。
メディアリテラシーしっかりしてるなと思った。
ファンの「重荷」を解放する優秀な戦略
こんプロラジオというポッドキャストで「自分の夢を託す形でアイドルを推すということ」について話題に上がっていたので、ポッドキャストの話題と混ぜてWhatmoreのファンへの向き合い方、従来のスターとの違いを感じた部分を書いていく。
ポッドキャストでは
- 年齢を重ねて自分の人生設計や夢を追いかけることが立ち行かなくなったときに、その夢を誰かに託したくなる。
- その先がアイドルを推すことで、間接的にせよアイドルは大勢の夢を背負わされるって相当重荷なんじゃないか。
- 託したくなる側の気持ちもわかるけどね。
ということを述べていた。
気持ちはめちゃくちゃわかる。
僕は今年35歳で、友人との会話の中でも「ワナビーでいることに慣れきってしまった」といった内容の会話もしていて、同時に自分の人生の幅みたいなものをかっちり設定してそこからはみ出ないように生きることで幸せを感じている。無理をしない、怪我をしないみたいなこともそういう幅の設定に入ってる。
ももクロを追っていた時期はまだ20代前半だったし、夢を託すとか「はて?」って感じだったのと、性別が違うのもあって文字通り偶像と認識していた。
つまり自分を重ねるということは一度もなかった。
だけど、WhatmoreはNYユースのリアルを歌っているのと、やはり男5人が仲良くわちゃわちゃ物作ってるというのは、より自分の気持ちを乗せやすいというか。純粋に羨ましい。
まさにこんプロで言っていたような夢を託すみたいなやっかいな感情になりそう。
俺はダメだったけど君たちは頑張れ みたいな。
Whatmoreが「お前たちと一緒に成長して景色見せてやんよ」的なノリだったら「託した」つって乗っかってたと思う。
ただ、彼らは違った。流石は令和を生きる若者で、ファンに見せたいビジョンというのがインタビュー動画で語られてた。
01:33:46
要約するとこのWhatmoreというプロジェクトを通じて、「誰かをインスパイアし、友人たちとクールなことをやりたいと思わせること」が最大の目標だと。
それと「Ratatouille(レミーのおいしいレストラン)」のセリフを引用し、「Anyone can cook(誰でも料理できる)」というメッセージ、つまり「誰でもクリエイティブになれる」という考えを伝えたいと言っていて、20代前半でこの考えを持ってるの時代の屍をちゃんと観察してるなと思った。
従来のスターが背負わされるファンの夢というのを上手いことズラして、抜け感のある秀逸な回答。
いい感じのコンテンツ見つけたし、もう寄りかかったほうが楽だからと思っていたところで、自分で立って歩きたいと思ってほしいみたいな投げかけは食らっちゃった。
実はまだアルバムすら出てない
Whatmoreについて色々と書いたけど、実はまだファーストアルバムすら出てないグループなのだ。
10/17にアルバムリリースされるみたいなので、どんな楽曲が入っているのか楽しみ。
そして彼らについて語れるファンがもっと増えたらいいなと思う。
WHATMORE – Upcoming Album by WHATMORE | Spotify