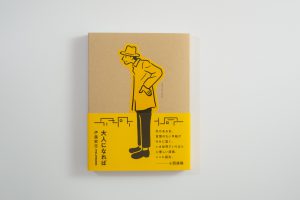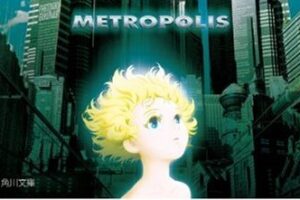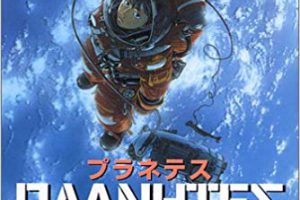先日、エルド吉水氏の漫画『ヘンカイパン』を読みました。その圧倒的なスケールと哲学的な深みに、まさに心を揺さぶられる体験でした。
まずは、この作品の根幹にあるタイトルから紐解いていきたいと思います。
『ヘンカイパン』というタイトルは、ギリシャ語の「Εν και παν」に由来しており、「一にして全(いちにしてぜん)」という意味を持つようです。
作中で使われている「世界のすべては神である」というセリフはタイトルにも通じており、汎神論や哲学も作品の主要なテーマとなっています。
序盤は、アスラという人物がニーナという何者かの声のままに世界を壊すシーンから始まります。
その後、精霊を名乗るオンビアサ、ジョフク、ホンガの三人に加え、彼らのまとめ役である導師ペマジュに会いますが、ニーナもその一人であることが判明します。当初、4人の精霊の意見を聞き、導師ペマジュが最終的に人類と地球をどうするか「審判」を下す予定でしたが、ニーナが単独で地球上の生命を断つと決め、アスラを従えて破壊活動をしていたことが判明します。人間だけでなく神々も対立し始め、物語に勢いがついてきます。
人類の罪を認めながらも地球の生命に新たなチャンスを与えようとする導師ペマジュ指揮下の精霊たちと、彼らとは対立し、ニーラの意志を体現するアスラとの間に激烈な葛藤が生じるのが、この『ヘンカイパン』の主な筋立てです。
読み進める中で、このペースと壮大さでは、一冊にまとめきれるのかと懸念しましたが、物語中盤以降は怒涛の絵力とドライブ感でストーリーが展開され、その不安は杞憂に終わりました。
特にアスラが覚醒するシーンは美しくも力強く、非常に印象的で必見です。
そして、このドライブ感で物語を牽引する上で、戦闘神として描かれる阿修羅を主軸に置いたのは見事だと思いました。
阿修羅と化したアスラの圧倒的な力と、導師ペマジュが下した審判によって物語はラストへ進んでいきます。
アスラが阿修羅と化してからの数ページで、それまで敵意を向けていた人類を瞬く間に戦闘不能状態に追い込む描写は、その圧倒的な力をまざまざと見せつけます。
特筆すべきは、それまでリアルタッチだった絵柄が、この戦闘シーンでは浮世絵の波のようなポップな線で表現されている点です。 これにより、それまでのリアルな世界とは一線を画した、まさに別次元の戦闘であることを強烈に印象づけ、物語にさらなる勢いを与えています。
この見開きもまた必見です。
阿修羅は単なる破壊の象徴にとどまりません。 神でありながら人間的な葛藤を抱える側面を持つ阿修羅をアスラに重ねることで、彼女の行動には単なる暴力ではない、より深い意味合いが込められていると感じさせられました。 このキャラクター選択こそが、怒涛のストーリー展開を可能にし、戦闘神にふさわしい、物語の核心を成す役割として美しく機能します。
この壮大さをたった1巻でまとめている点が非常に好みです。
おそらく、描こうと思えば20巻くらいかけて人類側と個々の精霊の掘り下げ、そして人類が地球に対して行ったことを細かく描写できたでしょう。
絵がハチャメチャにお上手なので。
しかし、エルド吉水氏が45歳から漫画を描き始めたことを考えると、作家人生において『ヘンカイパン』だけに力を注ぐのは、時間的な制約もあったと推察されます。それでも、この壮大なスケールと哲学的な問いかけを内包した物語を描ききり、1冊にまとめたことには、ある種の怒りに近い若々しさと力強さを感じました。
人類を破壊する描写や、阿修羅の内から噴き出す怒りといった表現は、まさにその怒りの感情を視覚化したものなのでしょう。これは社会や人類に対する普遍的な問いかけを含んでいると同時に、エルド吉水氏自身の内なる創作への衝動、妥協なき姿勢から来るものであるとも感じられました。それは、永井豪の『デビルマン』を彷彿とさせる、人間存在や世界のあり方に対する根源的な問いと、それに伴う破壊の衝動に近いものがあると感じました。
彼の絵柄は、手塚治虫の系譜から劇画の迫力までを内包した熟練の技を感じさせますが、その圧倒的な画力と物語を力強く牽引する勢いには、紛れもない若々しさが宿っています。現代に蔓延する売れ線作品とは一線を画し、まるで映画を観るような重厚な漫画表現は、ある種の頑固さや、自身の表現に対する強い信念を感じさせます。
言葉による明確なメッセージ性というよりも、その「絵力」と「描ききったパワー」が、直接、言葉にならない何かの感情を訴えかけてくるのです。
そしてラストページでは、ほぼベタ塗りのページが現れます。
このページをよく見ると、かすかに白い点がいくつかあり、俯瞰した宇宙空間のショットで終わっているように見受けられます。
この描写から、精霊たちが地球という舞台で戦い、最終的にはペイル・ブルー・ドット的な視点まで引いたのだと感じました。
人間よりも上の次元にいるはずの精霊たちが、人間と変わらず対立し、争う様が描かれた後、最終的にその視点が地球という舞台全体、さらには宇宙空間へと引かれるのです。この広大な宇宙的視点への移行は、壮絶な戦いの高まった熱を冷ます役割を果たしていると感じました。
彼らの対立や争いも宇宙の広大さの中では、ほんの1ドットに過ぎないという虚無的な感覚と共に、地球の運命がアスラに委ねられ、彼女がその選択を受け入れるかのように地球の付近を漂う姿にも、静かで冷徹な受容の雰囲気を感じます。
この「宇宙的視点」は、「一にして全」というタイトルが示す真理と深く繋がっています。
個々の存在がどんなに大きな力や争いを繰り広げようとも、最終的には宇宙という「全」の一部に過ぎないという、より普遍的な真理を示唆しているのではないでしょうか。その「1ドット」の中には、これまでの壮絶な物語や、無数の生命の営みが凝縮されており、そこには「尊さ」や「普遍性」が宿っていると感じました。
激しい争いの「熱」が冷め、宇宙の「冷却」された広がりの中に戻ることで、個別の物語が「一」なる宇宙へと還元され、全体の一部として統合される。つまり、私たちの喧騒も、神々の争いも、最終的には大きな宇宙のサイクルのなかの「一過性の出来事」であり、すべてが大きな「全」の一部として存在している、というメッセージを伝えているのかもしれません。
「Don’t think, feel」(考えるな、感じろ)という言葉がまさに当てはまる作品ですが、現状の世界情勢や神に近い存在になるかもしれないAIとカオスと化したインターネットなど、さまざまな方向からこの作品と接続できる気がします。
刺さらない漫画が大量に増えている中で、このような良い作品に出会えたことを嬉しく思います。
まだ半年ありますが、今のところ2025年に日本で発売した中でNo.1の漫画です。